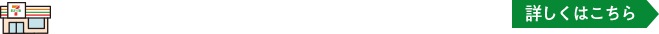出産内祝いの「のし」と「水引」、
その歴史やのし紙の書き方・掛け方を解説

出産内祝いから始まり、長寿のお祝いまで、人生の節目にはさまざまなお祝い事があります。このお祝い事の贈り物に欠かせないのが「のし」です。この「のし」とともに、ふさわしい結び方の「水引」を用意します。
この「のし」にも「水引」にも、一つひとつ意味があります。現在は「のし」も「水引」もすべて印刷された「のし紙」が用意されている場合もありますが、これらのしきたりの意味を知っておけば、より迷わずに選ぶことができるでしょう。今回は、出産祝いで使われる「のし」の歴史、正しい「水引」の本数や結び方、「のし紙」の書き方・掛け方をご紹介します。
「のし」や「のし紙」について、出産内祝いにふさわしい「水引」の正しい本数と結び方

「のし」の歴史は、神様のお供え物である「鮑」が始まり
祝儀袋やのし紙などの右上にある、お祝い事のみに添えられる飾りを、「のし」といいます。「のし」は「のしあわび」の略で、「鮑を薄く長くはぎ、引き伸ばして乾かしたもの」がルーツです。古来より鮑は貴重な食材で、神事のお供え物として用いられてきました。そもそも、神へのささげものとして新鮮な肴を供えることが、日本の贈り物の始まりだったのです。
乾燥した鮑は栄養価が高く長持ちするので保存食、不老長寿の印として重宝され、代表的な贈答品でした。鮑以外のものが贈答品に用いられるようになっても、鮑は引き続き添えられ、それが現在の小さなのしに変化したといわれています。
今は印刷されて略式になっていますが、その中央にかかれた黄色い部分が、かつての「のし」を表しているのです。
昔はのしあわびを重ねたものを、紙で包んで使っていました。のしは清浄という意味もあり、品物だけでなく贈り主の気持ちも表現しているといえます。一般的に、慶事にのみ使われ、弔事の場合には「生臭ものを忌み嫌う」ということから使わないもの、とされてきました。また、魚介類・肉・鰹節・塩干物などを贈るときにも、本来は使われません。
ただ現在では、冠婚葬祭を問わず、総合的にのし紙やのし袋という事が一般的です。デパートなどではお供えにも、「のしはいかがなさいか?」などと聞かれるので、その際に「弔事で使います」と伝えると、のし(のしあわび)のないかけ紙を用意してくれます。
のし紙とはどんな紙?
のし紙とは、奉書紙に「のし」と「水引」とを印刷したものです。「のしのあるかけ紙」をのし紙と呼び、特別なことや高額品を贈るとき以外は、のし紙をかけて贈るのが一般的です。のしは一般の贈答や慶事に使われるので、法事・仏事などにはのしがありません。水引だけを印刷したものが使われます。のし紙とかけ紙の違いはここにあります。
出産内祝いの「水引」、正しい本数は?
出産内祝いで使うのし紙には、水引の本数が5本か7本のものを使います。一般的な贈答や慶事には紅白の水引を使い、結婚祝いや高価なものを贈るときなどは、金銀の水引も使われます。水引の本数は、3本、5本、7本と奇数のこよりを束にして使うことが多いですが、その中でも5本を一組にして使うことが多くなっています。本数は、目的や包みの大きさ、金額などによって本数が異なります。
出産内祝いの「水引」、最適な結び方は?
出産内祝いの時に多い結び方は、紅白蝶結びです。出産は何度繰り返してもおめでたいことであるため、ほどけやすく、何度でも結ぶことができるもろわな結びが主流となっています。最近では水引があらかじめ紙に印刷されたものを使うことも増えてきましたが、以前は贈り主が自分で紙を包んだり水引をむすんだりしていたものです。水引には包みをとめるだけでなく、結び目で贈り主の気持ちを表す役割もあるのです。
結婚祝いと出産祝いを同時にいただいた場合に気をつけること
赤ちゃんを授かってからの結婚の場合、結婚祝いと出産祝いを同時にいただくこともあるかと思います。この場合、相手のことも考えてまとめて内祝いを贈ることもできますが、水引の種類には注意しなければなりません。結婚内祝いの水引は、出産内祝いとは違い、ほどけない結び切りを選ぶ必要があるからです。
贈る時期は、結婚式や出産を終えた後はイベント続きで忙しくなってしまうので、お宮参り前後がおすすめです。相手側も無事に出産できたか気になっていると思いますので、近況を簡単に書いたメッセージをつけるようにするのが礼儀でしょう。親しい方には手渡しでも良いですし、遠方の親戚には家族写真などを入れると喜ばれます。
出産内祝いの「のし紙」の書き方
いざのし紙に名前などを書き入れようとしても、「表書きには何と書けばよいのか」、「のし下には親と子供、どちらの名前を入れるべきか」など、戸惑ってしまいますよね。そこで、出産内祝いの場合の「のし紙」の書き方をまとめました。
出産内祝いの「表書き(のし上)」の書き方
最近では業者に依頼することが多い表書きですが、慶事には濃い墨を使います(弔事では逆に薄墨が多く用いられます)。文字はあまり崩しすぎずに、楷書か行書で、筆または筆ペンを使います。中心を意識して、水引に字がかからないように注意しましょう。
水引を中心としたときの上部、のし上の表書きは、贈り物の内容を書きます。出産内祝いの場合は、「内祝」と書きます。御礼やお返しなどの言葉は「もらったので返します」という意味になり内祝いの本来の意味とは異なりますので、使いません。ただし両親に贈る場合は、表書きは「御礼」としておいたほうがいい場合もあります。 表書きの文字を四文字にすると、死文字を連想させるため縁起が悪いと思われる方もいるかもしれません。避けた方が無難でしょう。
「寿」「内祝」など表書きの使い分けは意外と難しいものです。「寿」は結婚、長寿などのお祝い事、おめでたい慶事全般に使います。「内祝」はさまざまなお祝い後のお返しに使います。ささやかに自分のお祝いをしたという意味なので、お返しだけでなくお祝いに感謝する気持ちとして贈ります。
出産内祝いの「名入れ(のし下)」の書き方
基本的には赤ちゃんの名前を書くことがほとんどです。名前をお披露目する意味もあるので、難しい漢字や読み方が何通りもある場合はふりがなを振りましょう。苗字を入れることもあります。ただし、地方によっては親の姓名を書き、命名札としての短冊に赤ちゃんの名前を書くこともあるようです。これは、子どもの成長を願い命名札を神棚や床の間などに貼っていた風習から来ており、今も残っている風習です。この場合は、命名札をのし紙の右上に貼ります。命名札とのしの表書きには、地域によってかなり差があるようなので、きちんと調べるようにしましょう。主に中国・四国・九州地方に多いようです。
双子・多胎児の場合の「名入れ」の書き方
赤ちゃんが双子、もしくはそれ以上いる場合も、基本的なマナーは同じです。名前は、右から左へ兄弟の順で記載します。
出産内祝いの「のし紙」のかけ方
配達で贈るなら「内のし」が最適
のし紙は、「外のし」(品物に包装紙をかけ、その上からのし紙をかける)と、「内のし」(品物にのし紙をかけてその上から包装する)場合があります。本来、のしは贈り物に添えて風呂敷に包んで届けていました。その風呂敷の役割を考えれば、「内のし」が良いでしょう。また、出産内祝いは基本的には自分のお祝い事であり、控えめな方が好まれるとされているため、その観点からも「内のし」の方が最適だと考えられます。宅配便を使うことが多くなってきた中では、配達途中でのし紙が破れたりしてしまうのを防げます。
相手に直接手渡しするなら、「外のし」もアリ
外のしは、直接贈り先の相手に手渡しする場合など、すぐに目的が伝わった方が好ましい場合に選ぶと良いでしょう。どちらも間違いではないので、どう渡すかで判断します。
贈り先によっては、デザインに凝ったのしを使うと、相手も喜びます。花柄やハート、写真入りなどが人気です。大切なのは、贈る相手への配慮です。赤ちゃんの写真が負担に感じてしまう方もいると思われるので、赤ちゃんの写真を使用した品物を贈るのは親しい友人や親戚などにとどめ、それ以外の方、年配の方や上司などには定番のものを贈るようにします。
のしが付いていない贈り物を頂いた場合も、のし付きで内祝いを贈ります。ですが、もしお菓子などで贈り物が小さくなる時は、のしもかけ紙ではなく短冊タイプでも良いでしょう。
より丁寧に気持ちを伝えたいと思った時、のし紙の上にリボンをかけたくなる方もいるかもしれませんが、のしやのし紙をかけることは、それだけでより丁寧に贈り物をする気持ちを表現しているので、必要ありません。また、和洋折衷ともなりますので、併用はしない方が良いでしょう。
「のし」・「水引」のしきたりを守り、相手に感謝の気持ちを伝えましょう
「のし」の基本的な意義は相手を大切に思う気持ちです。のし=熨斗の「熨す」は、押し伸ばしては何度も行うという意味から、延寿につながるとされていました。また、「水引」は水を引くと書きますが、水を引いた後の清々しさから、物事を浄化して邪気を払う力があるとされています。最近は内祝いの品物を購入するお店ですべて整えてくれるので、これらのマナーを気にする機会も少ないかもしれません。ですが、本来の意味を知ってしきたりを守ることで、自然と贈る相手を思いやる心が生まれてくるのではないでしょうか。
相手に感謝の気持ちをきちんと伝えるためにも、本来の意味合いを知っておきつつ、正しく「のし」や「水引」、「のし紙」を使いこなしたいものですね。

-
笹西 真理
株式会社 トゥルース代表取締役
社団法人 日本マナーOJTインストラクター協会 創設者会長
マナースクール「Grace」主宰元国内系国際線CAとして5年半実績を積んだ後、大手コンサルティング関連会社において、飲食・小売関連の販促・広告戦略を主とするコンサルタントとして活躍。2005 年に株式会社 Truth を設立。飲食・物販・SC・各種団体・大学など、マナー・接遇・コミュニーションを中心とした社員教育、人材育成に携わる。また、2010 年一般社団法人日本マナー OJTインストラクター協会を立ち上げ、代表理事に就任。現在、約 400 名の講師と共に「サービス業の未来を輝かせる」をミッションに全国を飛び回る。
▼著書
『どこまでOK?がすぐわかる! 冠婚葬祭の新マナー大全』(成美堂出版・2019年2月出版)、『気くばりの教科書』(泰文堂)
『いつもうまくいく人の習慣』(リンダパブリッシャーズ)