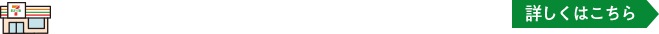出産内祝いに関するマナーやおすすめのギフトとは
内祝いは本来、身内の慶事を祝う贈り物で、お祝いをいただいたかに関わらず、身近な人に配ったり、家に招いておもてなしをするなど、あくまでも身内内でお祝いをするものでした。現在では、「お返し」と考えることが多くなり、地域による違いはあるものの、出産祝いを贈ってくれた方にお返しとして内祝いを贈るようになりました。出産内祝いはどのようなタイミングでお送りすべきなのか、またどのくらいの金額の品物を贈れば良いのか、迷ったことのある方も多いかもしれません。相手に快く品物を受け取ってもらえるように、出産内祝いのマナーについてチェックしてみてはいかがでしょうか。
出産内祝いの基本とは

出産祝いをもらったら、早めにお礼を伝えましょう!
出産祝いをいただいたらお贈りするのが内祝いですが、出産祝いへのお礼に関しては、可能な限り早めにお礼の電話をいれた方が良いでしょう。もしお祝い金をいただいた場合は直接お礼を伝えた方が、相手にも喜ばれ丁寧な印象を与えます。その後、改めて内祝いを相手にお贈りし、感謝の気持ちを伝えましょう。
出産内祝いには、赤ちゃんのお披露目といった意味も込められています。ですので、内祝いを贈る時は、「家族共々、これからもよろしくお願いします」という気持ちも忘れずに相手に伝えましょう。
出産内祝いの品物の金額相場はいくら?
お返しの品の金額相場は、出産祝いの三分の一から半額程度を目安にしましょう。両親や祖父母などから高額なお祝いをいただいたときは、そのお祝いの三分の一もしくは四分の一くらいの金額の品物を贈りましょう。
また、品物を返すだけでなく、近況の報告や赤ちゃんの写真をおくるなど、継続的にコミュニケーションを取ることで、感謝の気持ちを伝えます。
出産内祝いを贈るのに最適なタイミングとは?
出産内祝いを贈る時期は、生後三十日前後とされています。この時期はお宮参りの時期でもあり、お宮参りの準備にも忙しくなりますので、早めに贈る準備をしておくべきでしょう。お返しは赤ちゃんの名前で贈ります。
もし出産内祝いを贈るタイミングが遅くなってしまった場合は、内祝いの品物と一緒に、お食い初めや桃の節句、端午の節句など節目の行事を祝った際の写真を、遅れたお詫びと共に贈るのはいかがでしょうか。
出産内祝いは直接贈るべき?宅配でも大丈夫?
内祝いを贈る際、親しい間柄であれば直接赤ちゃんを連れて会いに行っても良いでしょう。しかし、訪問は、時に相手にも少々重荷になる場合があります。そのため、宅配が一般的になりつつありますが、その場合には事前に連絡を入れるようにしましょう。相手も予定を合わせられますし、万が一届かなかった場合も対処しやすくなります。
出産内祝いのマナー

品物にはメッセージを添えること
出産内祝いを贈る場合は、必ず出産祝いのお礼や赤ちゃんの様子を書いたメッセージを添えます。身内や親しい間柄の方には、赤ちゃんの写真を添えても喜ばれるでしょう。逆に、あまり親しくない方の場合、子どもの写真を贈られてもどうして良いか分からず、相手の負担になることもあるかもしれません。赤ちゃんをお披露目したいなら、顔を合わせるときに写真を持参して見てもらうようにしましょう。
連名で出産祝いを贈ってくれた同僚などにも、それぞれの人にお返しをしましょう。出産祝いの大体の金額を人数で割り、その半額を目安に品物を選びます。もしお花などを贈ってくれた場合には、皆で分けられるお菓子に「職場のみなさんで召し上がってください」などのメッセージをつけて贈ります。いただいたものよりも高額なお返しは、かえって相手に失礼にあたります。
内祝いの表書き・のし紙への書き方
内祝いの贈り方は、まず表書きを「内祝」とし、赤白の蝶結びののし紙に赤ちゃんの名前を書きます(地方によっては、のし紙は赤ちゃんの名前の両脇に「犬張子」と「でんでん太鼓」の絵が印刷されたものを選びます。犬張子とは犬の形をした紙をはった竹細工のおもちゃのことです。これら2つの飾りには、「子どもの成長を願い、邪気を祓い子どもを守る力がある」とされています)。赤ちゃんの名前にはふりがなを振ると親切です。品物には、親の名前で挨拶状を添えましょう。
【贈る人別】 出産内祝いにおすすめのギフト

出産内祝いの品物、定番の商品は何?
出産内祝いの品は、以前はお赤飯や紅白餅などを贈る風習がありましたが、最近は多岐にわたる品物が用意されています。食品を選ぶ場合は、宅配で贈っても問題ないように、賞味期限が長めに設定されているものを選ぶと良いでしょう。お菓子なら焼き菓子やおせんべい、暑い時期でなければチョコレートなどもおすすめです。傷みの早い果物などは不向きなので避けましょう。
定番の品物としては、食品では鰹節・お吸い物詰め合わせ・調味料詰め合わせ・コーヒー・紅茶・洋菓子・和菓子などがあります。日用品としては、漆塗りの丸盆・命名皿・グラスセット・ティーカップ・フォトフレーム・風呂敷・タオルセット・寝具・石鹸などが定番です。贈る相手との間柄を振り返って、喜んでいただけそうな品物を検討してみましょう。
職場の方に贈る場合
職場に贈る場合は、上司も含まれるので、マナーには気をつけたいところです。お菓子や飲み物など、後に残らない消えものを贈れば間違いないでしょう。赤ちゃんの写真と同じく、赤ちゃんの名前の入った品物は扱いに困ると思われますので、避けましょう。
上司への品物は、量よりも質にこだわるようにし、食べ物を贈る際は食べきれるように量は控えめにします。
職場の場合、連名で贈られる場合も多いと思われます。仲の良い同僚の場合は、個別に小物などを贈っても喜ばれるでしょう。
友達に贈る場合
友達なら、相手の好みも十分に理解している場合が多いでしょう。趣向を凝らし、喜んでもらえるようなものを贈りたいですね。出産内祝いらしい、やさしい雰囲気や赤ちゃんの肌を思わせる手触りの良いものなどはいかがでしょうか。女性には低刺激にこだわったタオルなどボディケアグッズ、ネイルやフェイスケアに使えるアロマなど、自分で買うには少し贅沢品といったものも喜ばれそうです。男性には実用的なものが一番。好みに応じてコーヒーや辛いものが好きなら高級レトルトカレーなど、すぐに消費できるものが良いでしょう。小物なら、ベーシックな色や形のものを選びます。悩んだ場合は、相手の好みのものが選べるカタログギフトもおすすめです。
両親・兄弟姉妹に贈る場合
赤ちゃんが生まれ、喜びを共に感じることのできる両親や、兄弟姉妹にこそ、赤ちゃんの名前入りギフトを贈りましょう。今後もお世話になるという感謝を込めて「これからもよろしくお願いします」という気持ちをきちんと伝えます。さりげなく名前を入れた高級ブランドのスイーツ、生まれた時の体重と同じ重さのお米、フォトフレームとスイーツのセットなどはいかがでしょうか。赤ちゃんの名前や写真をラベルに入れたワインや日本酒などを贈っても楽しいですね。
また、出産内祝いとは異なりますが、出産後に妻が実家に里帰りをする場合、夫の立場から、出産後の実家での生活費に相当するお金や商品券、お菓子などをつけて挨拶をします。夫の両親からも妻の実家に後日贈り物をすると丁寧ですが、この場合は「御礼」ののし紙をつけると良いですね。
親族に贈る場合
祖父母や親戚の場合、相手の好みやライフスタイルを踏まえた消耗品や生活用品が良いでしょう。実用的で、重なっても問題ないものがおすすめです。成長期のお子さんがいる親戚には、いくらあってもうれしい家庭用洗剤やシャンプー&リンス、タオルのギフトセット、台所で使用できる調味料などが良いでしょう。祖父母にはスープのギフトセットなど、小食でも問題なく簡単に調理できるものが喜ばれます。健康を考えたものなら、一層良いですね。赤ちゃんの写真や名前が入ったものも、「今はこんなものがあるのね」と新鮮に感じてもらえるかもしれません。海苔や緑茶など「黒」をイメージさせるものは法事・仏事向けなので避けましょう。現在のカタログギフトはグルメ・お酒、生活雑貨、お取り寄せスイーツなど、種類も豊富です。相手の趣味に合わせたものをおくり、感謝を伝えるようにしましょう。
カタログギフトについて

種類の豊富さや、相手の好みに合わせて贈ることができるカタログギフトなら、贈ることを避けなければならないものを贈る(相手が選ぶ)ことができます。
例えばグラスや鏡などは割れ物として縁起が悪いとされていたり、別れを連想させるといわれるハンカチなども、カタログギフトなら問題ありません。
メッセージを添えて気持ちをきちんと伝えることを忘れないようにしたいものです。
時代によって変化する出産祝いと出産内祝い
内祝いは自分たちで祝う自祝(じいわい)から、「誕生を内々に祝いました。赤ちゃんの名前は○○ですので、どうぞよろしくお願いします」というお披露目の意味をもつものとなりました。赤ちゃんと三世代で同居をする家が多かった時代には、父方の実家からは出産祝いを贈らないかわりに、出産内祝いを行っていたそう。一方、母方の実家からは祝い着やこれからの節句飾りなどを贈るのが一般的でした。しかし、現在では核家族が増え、しきたりにこだわることなく、ベビーカーやチャイルドシート、現金を両家から贈るケースも多くなりました。時代によって変化する出産祝いと出産内祝い。マナーに気をつけて、誕生の喜びをお互いに分かち合えると良いですね。

-
笹西 真理
株式会社 トゥルース代表取締役
社団法人 日本マナーOJTインストラクター協会 創設者会長
マナースクール「Grace」主宰元国内系国際線CAとして5年半実績を積んだ後、大手コンサルティング関連会社において、飲食・小売関連の販促・広告戦略を主とするコンサルタントとして活躍。2005 年に株式会社 Truth を設立。飲食・物販・SC・各種団体・大学など、マナー・接遇・コミュニーションを中心とした社員教育、人材育成に携わる。また、2010 年一般社団法人日本マナー OJTインストラクター協会を立ち上げ、代表理事に就任。現在、約 400 名の講師と共に「サービス業の未来を輝かせる」をミッションに全国を飛び回る。
▼著書
『どこまでOK?がすぐわかる! 冠婚葬祭の新マナー大全』(成美堂出版・2019年2月出版)、『気くばりの教科書』(泰文堂)
『いつもうまくいく人の習慣』(リンダパブリッシャーズ)