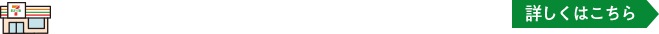贈る相手によって出産祝いの相場は変わる!
出産祝いを贈る際のマナーやおすすめの品物

いつの時代でも、赤ちゃんの誕生は、家族だけでなく、親戚、友達など、多くの人を笑顔にしてくれますね。そんな赤ちゃんが生まれてきてくれたこと、そして赤ちゃんを含めたご家族の幸せを願って贈るのが、「出産祝い」です。今回は、出産祝いを贈る時に迷ってしまいがちな金額の相場、おすすめの品物をまとめました。どのような物を贈ったら相手のご家族が喜んでくれそうか、考えながら参考に読んでみてもらえると幸いです。
【贈る相手別】出産祝いの相場

お祝いは高ければいいというわけではありません。高価なものは相手がお返しをする際に負担になってしまい、かえって迷惑をかけてしまいます。また、結婚祝いでは割り切れる金額は縁起が悪いとされていますが、出産祝いの場合は偶数でも問題ありません。
出産祝いは、贈る相手との関係によって相場が異なってきます。もしまだ自分が学生だったり、就職したばかりで余裕がない場合は、相場より少なくても問題ありません。また、相手が年下の場合は、少し多めにすることもあるでしょう。
どの場合も、おめでたい出産を祝いたいという気持ちを相手にきちんと伝えることが大切です。その上で、おおよその相場を確認してみてください。
父母 5万円~10万円
家庭の状況によって変動します。「両家で大きく金額の開きがある」というトラブルが起こりがちですので、両家で同じくらいの金額や品物を贈るように話をあわせておけるとよいでしょう。
兄弟姉妹 1~3万円
兄弟姉妹には、1万円~3万円、余裕がある場合は5万円程度でも良いでしょう。ただし、自分より上の兄や姉には、無理のない金額で構いません。普段はあまり交流のない場合もふくめ、負担のない金額を贈ることが大切です。
親戚 5,000~2万円
親戚もまた、家族同然の付き合いもあれば、疎遠になっている場合もあるでしょう。無理に用意することはありませんが、付き合いの程度で家族と相談して決めましょう。
友人 5000円~1万円
個人的に友人へ出産祝いを送る場合は、5000円~1万円が一般的です。親友なら1万円、たまに会う関係なら、5000円が目安です。友人数名で出し合う場合は、「死」や「苦」などをイメージさせる4万円・9万円は避けるようにして、合計いくらにするかを考えます。
同僚・ご近所 3000円~5000円
仕事関係の場合は、職場のお祝いとして一人500円~1000円程度出し合って、まとめてお祝いを送るのが一般的です。個人的に送る場合は、5000円~1万円程度。直属の部下や後輩、お世話になっている上司などには、少し多めに包みます。
ご近所の場合は、気をつかわせない程度の金額でOKです。
※双方の実家などで現金を贈る場合は、赤ちゃん名義で通帳を作るのも気が利いた贈り物になるでしょう。また、婚家と実家で、金額のバランスを考える地域や、実家からベビー用品一式を贈る場合もあるようです。
出産祝いを贈る際のマナー

今度は、出産祝いにおすすめの品物や、贈るときに注意するポイントなどを紹介します。一般的に出産祝いの品物としては赤ちゃんグッズが選ばれることが多いですが、最近では頑張ったママをねぎらうグッズも喜ばれます。
おめでたい報告を受けたら、すぐにお祝いを贈りたくなりますね。ですが、ママは出産という大仕事を終えたばかりです。無事に生まれたこと、母子の体調が安定しているかを確認してから、用意しましょう。贈る時期は、お七夜(生後七日目の夜)からお宮参り(生後約1か月)の間に贈ります。身内やごく親しい間柄で、直接贈りたい場合は、相手の体調をきちんと確認して、1ヵ月過ぎたころを目安に訪問します。もちろん事前に相手の了承を得ることが大前提です。
産後は体調も気持ちも不安定になりがちなので、その配慮も必要です。
すぐにでもお祝いの気持ちを伝えたい時は、メールや祝電、手紙などでお祝いメッセージを伝え、後日改めて出向くようにします。
ご祝儀袋や贈り物には、何度あってもうれしいお祝い事なので、紅白の蝶結び(花結び)の水引を用意します。のしをつけ、表書きには「御出産御祝」「祝 御出産」、下段にはフルネームで自分の名前を書きましょう。
できればボールペンや鉛筆よりも毛筆か筆ペンを使うようにしたいもの。筆ペンで書く場合には、慶事を意味する濃い墨の色を選びます。
お札は新札を用意するのがマナーです。お札の向きは、ご祝儀袋の中の内袋の表とお札の表を合わせると、相手がお札を取り出したときに肖像画が見える状態になります。
出産祝いにおすすめの品物

気心が知れた仲なら、思い切ってリクエストをしてもらうのも良いでしょう。リクエストが特にないのであれば、ベビー服やおもちゃなど、いくらあっても困らないものなどが一般的。本格志向の方や目上の人なら、好きなものを選んでもらえる商品券も喜ばれます。まずは、贈る人目線での出産祝いの品物の選び方を紹介します。
友人からの出産祝い(3000円~5000円程度)
・おむつやおしりふきなどの消耗品をかわいく詰め合わせてギフトに。お祝いとしては少し地味ですが、これから必ず使ってもらえるのでニーズが高いです。
・第一子以降の出産の場合、衣類やおもちゃはすでにたくさんあるという方も多いでしょう。その場合は、知育絵本や意外にママが自分で買わないものなども喜ばれます。
・友達数人で高級なお品をプレゼントするのも良いでしょう。友人や同僚数人で「ベビーシャワー」としてベビーカーやチャイルドシートなどを贈ることもできます。相手も買わずに楽しみにしてくれるはずです。ただし、高級なお品は親族も用意されていることが多いので、重複することがないようあらかじめ確認しておきます。
祖父母からの出産祝い(10000円以上)
孫の誕生は、子どもとはまた一味違った喜びがあるでしょう。特有のしきたりがある地方や家は別にして、ある程度のまとまった金額のものを贈りたいと考える方も多いと思います。その場合はパパ・ママに希望を聞きましょう。赤ちゃんにお兄さんやお姉さんがいる場合は、ささやかなプレゼントを添えるとさらに喜んでもらえるでしょう。
また、品物を贈る相手基準での選び方を紹介します。赤ちゃんの場合とママの場合を見てみましょう。
赤ちゃんへ(3000円~5000円)
赤ちゃんに贈る場合は、安心・安全で上質な素材のものを選びましょう。おもちゃは知育玩具が良いですね。一番人気のベビー服は大きめの外出着に、食器は普段使いできるような竹や木製、メラミン素材が良いでしょう。その他、おしゃれなスタイ(よだれかけ)やファーストシューズ、赤ちゃんの健康を祈るベビースプーンなども人気です。
赤ちゃんの名前や誕生日をいれれば、他にはない特別なギフトになるのでおすすめです。
また、「ご両親がどんなにあなたの誕生を待っていたか」が分かる手紙を、赤ちゃん宛てとしてママに贈るケースもあるようです。
ママへ(5000円~10000円)
頑張ったママには、癒しグッズや便利な実用品はいかがでしょうか。天然由来成分の良い香りがする石鹸や入浴剤は、柑橘類やリフレッシュ系がおすすめです。産後休む間もないママも多いので、心や肌に安らぎと潤いを与えられるようなものは、とても喜ばれると思います。また、外出時にはとても荷物が多くなるので、コンパクトに収納できるような機能的でおしゃれなママバッグもおすすめです。自分の事が二の次になるので、実用品でもセンスのよいものを贈ると良いですね。授乳ケープやインナーウェアなども人気があります。
出産祝いをパパママに贈る際に注意すること
赤ちゃんの誕生というおめでたい出来事は、夫婦はもちろん両家のご両親にとっても、とても大きな喜びです。心のこもった贈り物をしたいと思うのは当然ですが、事前にどのようなものが良いか考えを伺いたいものです。とくに場所を取るものは、住宅事情によっては邪魔になることもあるので注意しましょう。
また、出産祝いを贈るタイミングが遅くなってしまった場合は、「御成長祝」「祝御成長」として贈ります。産後三ヶ月ごろまでは「御出産祝」、それ以降から1歳の初誕生日までは、「御成長祝い」が目安です。時期によっては「初節句」、「祝御食初」として贈ってもよいでしょう。
出産祝いとして避けた方が良い品物
かわいいベビー服は贈り物として人気ですが、新生児用は出産前からすでに用意されている場合がほとんどです。赤ちゃんの成長はとても早いので、外出できるようになる頃には結局小さくなってしまい、着られないまま終わることもあります。1、2歳になってから着れるようなものを贈りましょう。また、はちみつを含んだ食品、アロマ製品、土器陶器を中心とした釉薬、絵の具を用いた食器は避けましょう。
赤ちゃんの誕生を祝う気持ちが伝わる、ご家族に喜ばれる贈り物を用意しましょう
出産祝いには、赤ちゃん誕生を喜ぶ気持ちと一緒に、家族を守る責任が重くなる両親を労う気持ちも伝えたいものです。まずはそのご家族が何を贈られたら喜んでくれるのかを、第一に考えてみましょう。その上で、ご紹介してきた金額の相場やおすすめの品物を参考にしてみてください。
地域によってはお祝いの仕方も変わります。呼び方、時期、内容はそれぞれであることも多いのできちんと確認しましょう。

-
笹西 真理
株式会社 トゥルース代表取締役
社団法人 日本マナーOJTインストラクター協会 創設者会長
マナースクール「Grace」主宰元国内系国際線CAとして5年半実績を積んだ後、大手コンサルティング関連会社において、飲食・小売関連の販促・広告戦略を主とするコンサルタントとして活躍。2005 年に株式会社 Truth を設立。飲食・物販・SC・各種団体・大学など、マナー・接遇・コミュニーションを中心とした社員教育、人材育成に携わる。また、2010 年一般社団法人日本マナー OJTインストラクター協会を立ち上げ、代表理事に就任。現在、約 400 名の講師と共に「サービス業の未来を輝かせる」をミッションに全国を飛び回る。
▼著書
『どこまでOK?がすぐわかる! 冠婚葬祭の新マナー大全』(成美堂出版・2019年2月出版)、『気くばりの教科書』(泰文堂)
『いつもうまくいく人の習慣』(リンダパブリッシャーズ)