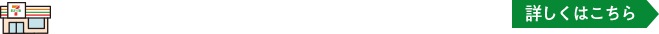香典返しにギフトカード・商品券を送るのはマナー違反?

香典のお礼として品物を送ることを香典返しといいます。仏式では忌明けとなる四十九日に忌明け法要を行い、喪主の挨拶状と一緒に香典返しを送ります。
現在では相互扶助的な意味合いとともに香典返しをもって告別式を行うようになりました。以前は、香典返しは葬儀で力を貸してくださった方の所へ伺い、無事に忌明けを済ませたことを報告し、その際のお礼として香典返しを渡していましたが、今は宅急便などを使って送ることが主流となりました。
また、基本的には香典の金額の半額、もしくは三分の一程度の品物を香典返しでは送ることがほとんどで、高級茶やブランドタオルなど、高品質なものを選ぶ方も多い中、最近では時代の変化を受け、利便性から高額の香典返しにギフトカードを送ることも多くなってきました。
このような変化がある中、失礼のないようにギフトカードを送るには、どうすれば良いのでしょうか。ギフトカードを送る場合のケースとともに、まとめてみました。
香典返しにギフトカード・商品券を送るのはマナー違反?

香典返しには、一般的に「後に残らない」ものが選ばれます。不祝儀を残さないという考え方から、ずっと後まで残ってしまうものを避けるようにします。お菓子やコーヒー、お茶などの消耗品、タオルや石鹸、洗剤、食器などの日用品が定番で、それぞれに意味があります。例えばお茶は、故人のことを思い偲びながら飲むことができ、タオルは仏の世界に旅立つ白装束に見立てられる、石鹸には、不幸を洗い流してくれるという考え方があります。食器も漆器は漆で悲しみを塗りつぶす、陶器は土に還っていく故人への偲ぶ思いなどが含まれます。逆に、刃物や、慶事に使われるお酒、生ものは避けた方が良いとされています。
後に残らず、日持ちがして、相手の好みが分かれにくいもの。それが基本的な香典返しの選び方ですが、その中で、最近定番になっているギフトカードは、この条件にもぴったりです。また、高額の香典返しの場合、それに見合う品物を選ぶのは大変で、配慮もより必要になります。
香典返しにギフトカードを送るのは、決してマナー違反ではなく、時代の流れに沿っているといえます。葬儀自体も家族葬など、コンパクトな内容に変化している時代です。香典返しも、利便性を考えその場でお返しすることも増えているようです。この場合、誰にいくら頂いたかを把握する手間も省け、住所の管理も基本的には不要です。香典返しの形が変わっていくのは自然のことでしょう。
香典返しにギフトカード・商品券を選ぶメリット、デメリット
香典や香典返しとは、互いを助け合う「相互扶助」の考え方で成り立っています。ですので、役に立たないもの、先方を不快にさせる、逆に気を使わせてしまうものでなければ、香典返しとして成立すると考えて良いでしょう。
香典返しにギフトカードを送るメリットは、まず無駄にならないということが第一でしょう。先方が時間のある時に、好きなものを選べるのは効率的で、失敗もありません。先方がどんなものが好みなのか、趣味が分からなくても安心できます。また、ギフトカード自体がとてもミニマルなので、送料も少なくて済み、こちらも香典返しの品物に何が良いのか、迷う必要もありません。価格帯も幅広く対応できます。包装・配送の手数料も、ギフトカードの場合はほとんどの販売店でサービスにて行っているようです。
逆に、デメリットは、やはりギフトカードは金額が明確にわかるので、先方が良い印象を受けないことも考えられるということです。通常の香典返しなら、わざわざ調べない限り、先方がその金額がはっきりわかるということはほぼありません。日本文化でも、贈答に関してははっきりとした金額で送ることは相手への配慮にならないとされています。
また、香典には「遺族に役立ててほしい」といった心遣いが大いに含まれていますので、その気持をそのまま返してしまうようなギフトカードでは、かえって失礼に当たる場合もあります。
やはり、目上の方、習慣を重んじる方には避けた方が良さそうです。
香典返しのギフトカード・商品券の送り方や注意点について
ギフトカードは現金ではないので、発送方法はこちらで選ぶことができますが、紛失の可能性もあるので、追跡サービスや保証をつけられる方法で郵送したり、書留を利用したりすることをおすすめします。
印刷されただけのお礼状では気持ちが伝わらないと思われる場合は、手書きのお礼状を添えると丁寧な印象になります。故人のエピソードを加えるなど工夫しながら、挨拶文のテンプレートを参考に書いてみましょう。
デパートなどで購入されることがほとんどかと思われるので、かけ紙など包装はそちらにおまかせすれば良いでしょう。お店によっては封筒などもあるかもしれません。 送る相手との関係によっては、ギフトカードにかけ紙をかけ、三千円程度の菓子をお盆代わりにして弔事用包装紙で包み、一緒に送っても良いでしょう。(その場合、菓子にはかけ紙をかけません)。先方がギフトカードに気が付かずに包装紙や箱を捨ててしまうことのないよう、お礼状に一言加えておきます。ギフトカードだけではなんとなく味気ない感じがするといった場合にもおすすめです。親しい間柄であれば、ギフトカードを送っても良いか聞いても失礼ではないでしょう。
また、ギフトカードといってもいろいろな種類があります。ネットショッピングに使えるものから、グルメカード、旅行用ギフトカードなどもあります。ものによっては、おつりが現金で返ってくるもの、チャージ式のカードタイプ、メッセージ印刷ができるものなど、非常に豊富です、決まったお店でしか使えないもの、先方の住んでいる地域では使える機会が少なそうなもの、おこめ券やビール券など先方の好みを制限してしまうものなどは避けるのが無難です。全国百貨店共通のギフトカードは高級感もあり、一番喜ばれるでしょう。
また、ギフトカードのほとんどはおつりが出ないので、先方が使いやすいよう、千円単位などで送るなどの気づかいがあるとなお良いですね。
香典返しは、地域性がとても強いものなので、必ずその場所での風習を確認しておきましょう。
失礼にあたると思われる方には、カタログギフトを選ぶのもひとつかも?

時代の流れとともに、ギフトカードを香典返しとして送ることはマナー違反ではなくなってきています。しかしマナーについて考えれば考えるほど、結局何にすれば良いのか分からなくなってしまうことも考えられます。金額がはっきりしてしまうことで、配慮や謙虚さが足りないと感じる方もいるかもしれません。そんなときにはカタログギフトはいかがでしょうか。
ギフトカードと同じく使い勝手がとても良く、金額がはっきりとは分からないので、安心して送ることができ、先方の年齢や好みにも幅広く対応できます。ジャンルも豊富で自由に選んでいただきながら、生前お世話になった感謝をきちんと伝えることができます。
先方の家族構成や、ライフスタイルの変化によって、使いやすいと思われるものも変化していきます。お送りしたけれど、お相手には使えないものだった、では気持ちが伝わりません。カタログギフトは、その心配をカバーしてくれます。自宅にいても商品を選ぶことができ、日常生活で使用できるベーシックなものが多いので、迷うことも少ないでしょう。
ギフトカードもカタログギフトも、使い勝手の良さと送られた側が自由に選ぶことができるのが共通のメリットです。送る相手が親しい間柄や若い方であればギフトカード、年配の方や外に出ることが不自由な方にはカタログギフトをおすすめする、というのもひとつの方法でしょう。
相手のことを考えて、スマートなお返しを
香典の持つ「相互扶助」の考えに思いを馳せ、相手の立場に立って配慮を行き届かせて、お返しをどうするかも考えたいもの。ギフトカードに対してどう考えるかはそれぞれなので、やはり誰にギフトカードを送るかを考えて選ぶことが最も重要になります。感謝の心を添えた小さな工夫を付け加えて、スマートに送りたいものですね。
(※)地域によって、慣習が異なる場合があります。品物を渡す際は、相手が住む地域の慣習を事前に確認しておくことをおすすめします。

-
笹西 真理
株式会社 トゥルース代表取締役
社団法人 日本マナーOJTインストラクター協会 創設者会長
マナースクール「Grace」主宰元国内系国際線CAとして5年半実績を積んだ後、大手コンサルティング関連会社において、飲食・小売関連の販促・広告戦略を主とするコンサルタントとして活躍。2005 年に株式会社 Truth を設立。飲食・物販・SC・各種団体・大学など、マナー・接遇・コミュニーションを中心とした社員教育、人材育成に携わる。また、2010 年一般社団法人日本マナー OJTインストラクター協会を立ち上げ、代表理事に就任。現在、約 400 名の講師と共に「サービス業の未来を輝かせる」をミッションに全国を飛び回る。
▼著書
『どこまでOK?がすぐわかる! 冠婚葬祭の新マナー大全』(成美堂出版・2019年2月出版)、『気くばりの教科書』(泰文堂)
『いつもうまくいく人の習慣』(リンダパブリッシャーズ)