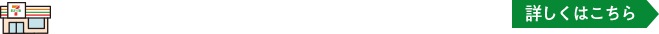香典返しに贈る定番品・タブーな品物とは?送る際のマナーと送るタイミングについても解説
香典をいただいた場合、その方には忌明けに挨拶を兼ねて香典返しを行います。四十九日の忌明け法要までは忌中なので、その間は令状や香典返しは控え、弔問の答礼は忌明け後にします。香典返しは「おかげさまで四十九日の法要を滞りなく相営み忌明けいたしました」という挨拶でもあります。ただし、最近では通夜・葬儀の場でお渡しする「即日返し」も増えてきています。
またキリスト教式の場合、本来、香典返しのようなしきたりはありませんが、カトリックの場合には三十日目の追悼ミサ、プロテスタントの場合には一ヵ月後の召天記念日のころに、故人を偲ぶような品物を添えて送ります。
このように香典返しを行うべきタイミングは、遺族の状況や宗派などによって異なります。また、香典返しの品物も、選び方を間違えると送り先の相手を驚かせてしまうこともあるかもしれません。そのようなことのないように、香典返しに最適な品物やタブーの品物を確認しておきましょう。あわせて、香典返しを送る際のマナーや送るタイミングもチェックしておくことをおすすめします。

香典返しの定番の品物とは
まず、香典返しの品物はどのくらいの金額のものを選べば良いのでしょうか。俗に「半返し」といわれるように、いただいた額の二分の一から三分の一の金額相当の品を送るのが一般的です。実際は、香典には不時の出費の相互扶助という意味もあるため、亡くなられた方の立場や関係をもとにして判断するのが良いでしょう。
通常の香典返しの場合、一人ひとりにそれぞれの金額に応じたものを探すのはとても大変なので、振り分けを行います。三千円までは千円、五千円までは二千円、一万円以上は五千円の品で統一するといった具合です。ただし、近年は香典の額にかかわらず同じ品物にすることも多いようです。
香典返しの品物は消耗品など、どこの家庭でも使える日用品が一般的です。これは、「不幸を後に残さない」よう「消え物」を送るという考え方が元になっています。たとえば麺、石鹸、コーヒー、タオルや毛布などを、金額に応じて3ランク程度に分けるとスムーズでしょう。同じ会社の職員など大勢が対象の場合は、分けやすい食品などにします。
(例)
・お茶、コーヒー、紅茶、お菓子などの食品
・石鹸、洗剤、タオルなどの日用品
・お皿、グラスなどの食器類
・ギフトカタログ
香典返しに選んではいけない品物とは何か

香典返しの定番品もあれば、香典返しに避けた方が良い品物もあります。例えば置物や、肉や魚などの生臭さが気になる生鮮食品、こぶ(昆布)や鰹節、ワインなど、おめでたいイメージがあるもの・「福」「寿」などが名前に入っているもの・赤や金などのパッケージのものが避けた方が良い品とされています。
(例)
・お酒などの嗜好品
・慶事に使われる鰹節や昆布
砂糖は香典返しの品物として選んでも大丈夫?
砂糖は華やかなパッケージのものが多いので、香典返しに選ぶには少し迷うかもしれません。ですが砂糖は慶事用だけではないので、問題ありません。昔は白い砂糖が貴重品で、その貴重なものをお供えする「供糖」というものがあります。葬儀のときなどに、白い砂糖と緑の砂糖を供えることもあります。
高額なお香典をいただいた場合や弔電のみをいただいた場合は、何をお返しすれば良い?
高額な香典返しに、お菓子とカタログギフトなど二品でお返しをすることがたまにありますが、仏事では「不幸が重なる」ことを連想させるとして、複数を嫌います。二品送る場合には、ギフトショップなどで一つに包んでもらうか、掛け紙だけに付けるのが一般的です。
その他、現金ではなく弔電だけの方や生花、花輪、お線香などを送ってきてくれた人には、忌明けの挨拶をかねて令状や挨拶状、感謝の気持ちを表すものとして菓子折りを送ると良いでしょう。特に生花は高額なものも多く、まとめてお返しをしたほうが良いのではと思われるでしょうが、香典返しと生花のお礼をまとめる場合、送り主が合算されていることに気が付かない場合もあります。ですので、別々にお返しをするほうが丁寧な対応といえます。
家族葬でお香典をいただいた場合、何をお返しすれば良い?
家族葬などの場合、香典を辞退することがあります。それでも香典が送られてきた場合は、それは気持ちとしていただきつつ、同額程度のお返しの品とお礼状をお送りします。入院見舞いをいただいたまま亡くなり、さらに香典がおくられてきた場合は、お見舞いのお返しを含めた香典返しをするか、「お見舞御礼」として季節のお菓子やタオル、お茶などの日用品をおくりましょう。「仏が重なる」として、同送を嫌う方もいらっしゃいますが、これは弔事用途の品物を二つ重ねて送る場合のことになります。この場合は用途が異なるので、問題はありません。
また、故人の遺志を尊重し、香典返しの一部を寄付するときには、少額の香典返しを用意し、寄付先や寄付の趣旨を記した挨拶状を添えます。寄付先によっては、故人の名前を入れた挨拶状を用意してくださる場合もあります。
香典返しを送るタイミングはいつ?

地域や親族間の慣習などもありますが、四十九日の忌明けを迎えた後に送るのがほとんどです。四十九日忌は、この日をもって忌明けとなる大切な法要であり、会食やお礼の用意など忙しくなります。ですので、香典返しは改めて送るのがおすすめです。初七日から忌明け法要の間に準備をはじめましょう。お通夜と葬式の香典帳を使ってリストを作ると便利です。「間柄」「氏名」「住所」[電話番号]「香典額」(品物)「香典返しの料金」「送料」「発送日」などをまとめます。
香典返しを送るのを避けるべきタイミングとは
香典返しが亡くなってから三ヶ月先になると良くないとされる「三月またぎ」は、弔事のお返しなどを三ヶ月にわたって行うのは良くないという、ある種のゲン担ぎです。とくに四十九日の法要が三ヶ月目にまたがることは「始終苦が身(三)に付く」ということで良くないと言われています。ただし実際には、月中以降に亡くなると忌明けが三ヶ月にまたがってしまうため、それを気にする知人などがいる場合には、事前に近しい親戚、ご住職さまなどに相談しましょう。
また、お盆やお彼岸はご先祖様を供養する大切な時期なので、できるだけその時期を避ける配慮も必要です。お盆やお彼岸に品物が届いて縁起が悪いということではなく、品物が届くことで先方をわずらわせたくないという気持ちを表す意味もあります。
三回忌法要でかなりの額の香典をいただいた場合は、基本的に引き出物で済ませます。法要後、一週間から十日後に先方に届くように、心ばかりの品を送りましょう。
※関西では忌日の数え方が異なります。法要を行う日は亡くなった日を入れて数えるのが一般的ですが、関西では亡くなった日の前日から数えることがあります。これは、忌日法要の前日を「お逮夜」といい、この夜に読経し、法要を行う習慣が関西にあるからです。法要を行う日が、関東では当日、関西ではお逮夜として前日になるため、忌日の数え方が違ってくるのです。
通夜・葬儀の場でお渡しする「即日返し」も、選択肢の一つ
最近は、通夜・葬儀の場で一律の品物をお返しする「即日返し」も増えています。「その場返し」ともいい、「会葬のお礼とこれをもちまして香典返しとさせていただきます」などの挨拶状をそえて渡します。
後で手配をする手間が省け、芳名帳の書き忘れでうっかりお返しができないという状況も防げます。送料はもちろんかかりませんし、リストを作る必要もありません。逆に香典の金額が分からないので、準備したものでは見合わない場合には、忌明けに再度香典返しを送ります。二万円以上の香典をいただいた場合は半返しで一万円を目安にしましょう。親族からの香典は一般会葬者より高額なことが多いので、四十九日法要に合わせてお返しをしたほうが良いでしょう。遠方の親戚など、宿泊費や交通費をかけている場合は、少し多めにお返しをするのが礼儀です。もちろん親族は「相互扶助」の目的が強いと考えられるので、額にとらわれなくても良いという考え方もあります。
喪中はがきを出した後にいただいたお香典、いくらぐらいお返しをすれば良い?
喪中はがきを出した後にいただいたお香典には、一週間から十日後に先方に届くよう、「志」(関西は「満中陰志」など)の掛け紙で、三分の一から二分の一の額を目安にお返しをしましょう。
四十九日法要のお返しと香典返しを一緒におくりたい場合もありますが、これらは同時に送るものではないことも覚えておきましょう。法要は前倒しに営むときもあり、順番としては法要のお返しが先になります。法要にいらした方へは、当日引き出物をお渡しし、法要には来られず香典だけ出された方には、香典返しが届いてから数日後に四十九日法要のお返しが届くようにします。
香典返しを送る地域、お店や業者をよく調べ、誠実な気持ちを相手に伝えよう

香典の整理は非常に大変です。例えば、「香典帳の文字が読みづらい」、「金額と香典帳の金額が合わない」といったトラブルが発生することもありえます。先述した香典のリストを作成するなど、香典返しをすることを考えて準備を行っておくと良いでしょう。
また香典返しの際には、品物選びももちろんですが、品物を扱うお店や業者選びも気をつけるべきポイントです。満足のいくお店、良い品物をゆっくりと吟味して探す時間をとるのは難しいでしょう。ですので、丁寧に対応してくれるかどうか、商品の品質が良いかどうかなど、サービスの優先順位を決めることをおすすめします。最近では、葬儀社が香典返しのサービスも扱っている場合もあります。香典返しは、送る側の気持ちを先方に伝えるものなので、細かいサービスに応じてくれなかったり、割引だけを売りにしたりするような業者には注意しましょう。
また、地方によって様々な習慣があるので、事前に調べておくべきでしょう。例えば、香典返しが大変になるため、香典そのものを辞退する地域もあるようです。現在の社会情勢を考えれば、そこまで長く深い付き合いというのも少なくなってきているため、合理的とも思えますし、お礼の習慣もさまざま。まずは信頼できる葬儀社を選び、そこに相談するのが一番ですね。
香典返しで、相手に最大限の感謝の想いを伝えましょう
香典返しは、送る相手の地域や宗派などで大きくルールが異なる場合があります。ですが最も重要なことは、忙しいなか故人を偲んで香典や弔電などをご用意くださった方々に、故人に代わって感謝の気持ちをお伝えすることです。そして、その想いがきちんと相手に伝わるようにするためには、可能な限りお相手の状況を配慮して品物をお渡しするのがベストでしょう。先方に気持ち良く香典返しを受け取っていただくためにも、できる限りの心配りはしておきたいものですね。
(※)地域によって、慣習が異なる場合があります。品物を渡す際は、相手が住む地域の慣習を事前に確認しておくことをおすすめします。

-
笹西 真理
株式会社 トゥルース代表取締役
社団法人 日本マナーOJTインストラクター協会 創設者会長
マナースクール「Grace」主宰元国内系国際線CAとして5年半実績を積んだ後、大手コンサルティング関連会社において、飲食・小売関連の販促・広告戦略を主とするコンサルタントとして活躍。2005 年に株式会社 Truth を設立。飲食・物販・SC・各種団体・大学など、マナー・接遇・コミュニーションを中心とした社員教育、人材育成に携わる。また、2010 年一般社団法人日本マナー OJTインストラクター協会を立ち上げ、代表理事に就任。現在、約 400 名の講師と共に「サービス業の未来を輝かせる」をミッションに全国を飛び回る。
▼著書
『どこまでOK?がすぐわかる! 冠婚葬祭の新マナー大全』(成美堂出版・2019年2月出版)、『気くばりの教科書』(泰文堂)
『いつもうまくいく人の習慣』(リンダパブリッシャーズ)