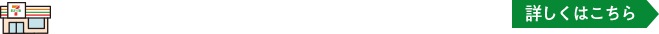香典返しにお礼は必要?お礼の伝え方を手紙・電話・メールごとに解説
香典とは、故人の冥福を祈り、手向ける香にかえて、金品などを供えるものです。実際には、不幸のあったお宅への経済的な支援という意味もあります。そのため、本来はお返しの必要がないものですが、現在は忌明けに、香典返しを送るのが一般的になってきました(仏式では三十五日か四十九日、神道では三十日祭か五十日祭、キリスト教では一ヶ月後の昇天記念日(プロテスタント)や三十日の追悼ミサの日(カトリック)に送るのが一般的)。
香典返しの品物をいただいた場合、つい先方にお礼を伝えたくなると思います。ですが、香典返しにお礼を返すのは、マナーとしてふさわしいのでしょうか。また、どうしても先方にお礼をお伝えしたい場合、どのような言い方をすれば良いのでしょうか。香典返しのお礼について、まとめてみました。

香典返しにお礼は必要?どうしても気持ちを示したい場合は?
では、香典返しにお礼は必要なのでしょうか。基本的には、香典返しでいただいた品物やあいさつ状には、お礼や令状は出さないしきたりです。遺族が悲しみをかかえている時なので、「ありがとう」とお礼を言うのはあまりふさわしくありません。また、二度と起こってほしくない不幸に対して礼を述べるのは、失礼にあたります。
遺族としても、香典返しを送ることで、辛い気持ちから少し離れるタイミングと思われますが、ここで香典返しのお礼をしてしまうと、また元の気持ちに戻ってしまうかもしれません。
とはいえ確実に届いたことを先方に知らせることも大切です。親しい間柄なら一言お伝えしたくもなりますね。品物がきちんと届いたことを伝えることで、遺族の心配事を減らせるという考え方もあるでしょう。
何らかの形で気持ちを示したいときは、葬儀のあわただしさがおさまり、あらためて悲しみや寂しさが深まる忌明けの頃に、お見舞状を出したり、親しい間柄であれば電話で力づけてさしあげたりすると良いでしょう。その際に「ご丁寧なごあいさつをいただきまして」と香典返しについてさりげなくふれます。
香典返しのお礼は、間柄を考慮して手紙・電話・メールで伝える
自然にお礼を伝えたい方におすすめなのは、喪中見舞いなどを兼ねた手紙を出すことです。その手紙には、品物について届いたことを報告するだけにとどめます。
親しい間柄であれば、電話で「ご供養の品をいただきました。恐れ入ります」などと伝えることはかまいません。近況を尋ねつつ、「ありがとう」「うれしかった」という表現は避けて話しましょう。ここからは、香典返しのお礼の具体例を紹介していきます。

(例)手紙
お礼を伝える方法として一般的です。会社の上司や目上の方であれば、お見舞状をはがきでお送りしましょう。法事、法要中の遺族は非常に忙しく、準備に追われながら、いろいろな関係者と連絡を取り合います。そのタイミングで電話をかけてしまっては、遺族に負担をかけることにもなります。手紙であれば、遺族が落ちついて一息入れられたときに読んでもらえるので、より無難な方法と考えられます。また、電話よりも丁寧な印象をもってもらえるでしょう。
内容は、香典返しがきちんと届いたこと、お見舞いの言葉、故人の冥福を祈る言葉をなるべくシンプルに書きます。短文になるので、一筆箋を使っても良いでしょう。前置きや時候の挨拶も省略します。
香典返しについてのお礼や品物をほめるような文章は避けます。使ってはいけない忌み言葉も法要に関係する手紙には多いので、失礼にあたらないよう注意が必要です。
「拝啓 ○○○○○○○の季節となりました。
本日ご丁寧な挨拶の品が届きました。何かとご心労が多いことと心配でしたが、却って恐縮しております。
その後いかがお過ごしでしょうか。
よろしければまたお食事でもご一緒しましょう。
○○○○○がそこまで来ています。
どうぞご自愛ください。敬具
○○年○月○日 □□ □□(名前)」
「前略
ご丁寧な品を頂きました。
お心遣いを頂戴し恐縮しております。
○○さんが急逝されもう1年ですね。
元気な笑い声や優しかった笑顔が今でも思い出されます。
△△さんもこの1年、とても大変な日々だったと思います。
どうぞこれからもお体を大切になさってください。
またお会いした時には一緒にお食事でも行きましょう。草々
○○年○月○日 □□ □□(名前)」
他にも、「皆様の寂しさはいかばかりかとご心中お察し申し上げます」「この度は、お心遣いを賜り、恐縮です」「志の品が届きました。お気遣い頂きまして恐れ入ります」などの書き出しも良いでしょう。
また、下記の点に注意して仕上げます。
- 「拝啓」と「敬具」は一緒に使います。
- 時候の挨拶を入れますが、親しい間柄なら時候の挨拶を省略して、「前略」と「草々」などを使います。
- 送る季節に合わせた言葉を加えます。
- めでたいものへのお礼ではないので、「ありがとうございます」は使わず、恐縮しています、という言葉で気持ちを伝えます。
- 相手を気遣う内容を本文に含めます。近況をさりげなく打診したり、簡単に自分の近況を伝えましょう。
- 個人の呼び方は、知り合いであれば○○さん、面識がない場合は、敬称にします。
祖父:御祖父様
祖母:御祖母様
父:ご尊父様、お父上様、お父様
母:ご母堂様、お母上様、お母様
夫:ご主人様、旦那様
妻:ご令室様、奥様
息子:ご令息様、ご子息様
娘:ご令嬢様、お嬢様 - 枚数は、不幸が重なるという意味を考え、便せんは一枚、封筒は一重にします。
- はがきであれば、時候の挨拶は省きます。絵柄はあっても問題ありませんが、おめでたいイメージのものは避け、さりげないワンポイントや無色、無地にすれば間違いありません。
- 最後にはがき、手紙を出す日付を入れます。名前も入れた方が丁寧でしょう。

(例)電話
直接気持ちを伝えたい場合は電話にしますが、注意すべきことがあります。忙しくしている遺族のことを考え、数分程度に済ませられるよう、電話をかける前に必ず伝える内容を整理しておきましょう。世間話や「ありがとう」などの表現は避け、香典返しが無事に届いたこと、法要で大変な思いをしている遺族への配慮にとどめます。
香典返しを送る数は非常に多いので、その度に電話がかかってくることを考えれば、簡潔に済ませることも気遣いになるのです。
「本日、お品を頂きました。どうぞお体に気をつけてお過ごしください」といった会話で良いでしょう。単純にお礼を述べるよりは、他の用事について話をして、ついでに無事に届いたことを伝えるとスムーズかもしれません。「くれぐれも」「ますます」は重ね言葉といい、悪いことを繰り返す意味があるので、使わないようにしましょう。
法要のスケジュールを見計らい、遺族が落ち着いたころに電話をするようにします。
「お香典返しが届きました。ご丁寧に恐れ入ります。
もうそんな時期なのですね。
その後いかがお過ごしですか?」
「今日、忌明けのご挨拶の品が届いたので、その後いかがされているかと思いお電話しました。
ご丁寧に恐れ入ります。
みなさんはいかがお過ごしでしょうか」

(例)メール
親しい友人である場合にはメールでも構いませんが、法要では基本的には避けましょう。簡単にやりとりできるため、「返信をしなければいけないのか」と遺族に余計な心配をかけてしまうことも考えられるので、注意しましょう。
文面のマナーは基本的に手紙と同じです。長々とした内容にならないよう注意して、香典返しがきちんと届いたこと、遺族を気にかける言葉のみにまとめます。
メールを送るときには「拝啓」「敬具」といった頭語は必要ありません。相手のお名前に続けて、直接本文を書いていきましょう。
「本日、お香典返しが届きました。
どうしているか気になっていたので、かえって恐縮しています。もうそんな時期なのですね。
その後いかがお過ごしですか?」
「本日、忌明けのお品を届けていただきました。ご丁寧に恐れ入ります。
その後いかがお過ごしかと思いメールをしました。
もうそんな時期なのですね。」
「本日、忌明けのご挨拶状が届きました。ご丁寧なお品もお送りいただき、かえって恐縮しています。
その後いかがですか。ご家族の皆様も落ち着かれましたか。」
など、ご家族を気遣う内容や「何かできることがあればご連絡いただきたい」といった言葉を最後に添えると良いでしょう。
喪主や施主となる相手のお気持ちを察し、一歩控えた行動を
冠婚葬祭の場面では、しきたりやマナーをわきまえた上での気持ちを込めたふるまいやお付き合いを心がけたいもの。ことに葬儀や弔事、法要ごとに関しては、喪主や施主となる相手のお気持ちを察し、状況に配慮した対応が求められます。いち早くお言葉をかけたい時も、遠方でお会いできない気持ちを形にして届けたい時も、お相手に配慮しながら想いを伝えることを忘れず、一歩控えた行動を心がけましょう。
(※)地域によって、慣習が異なる場合があります。品物を渡す際は、相手が住む地域の慣習を事前に確認しておくことをおすすめします。

-
笹西 真理
株式会社 トゥルース代表取締役
社団法人 日本マナーOJTインストラクター協会 創設者会長
マナースクール「Grace」主宰元国内系国際線CAとして5年半実績を積んだ後、大手コンサルティング関連会社において、飲食・小売関連の販促・広告戦略を主とするコンサルタントとして活躍。2005 年に株式会社 Truth を設立。飲食・物販・SC・各種団体・大学など、マナー・接遇・コミュニーションを中心とした社員教育、人材育成に携わる。また、2010 年一般社団法人日本マナー OJTインストラクター協会を立ち上げ、代表理事に就任。現在、約 400 名の講師と共に「サービス業の未来を輝かせる」をミッションに全国を飛び回る。
▼著書
『どこまでOK?がすぐわかる! 冠婚葬祭の新マナー大全』(成美堂出版・2019年2月出版)、『気くばりの教科書』(泰文堂)
『いつもうまくいく人の習慣』(リンダパブリッシャーズ)