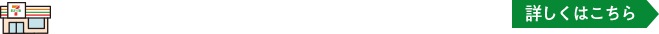結婚内祝いのメッセージに使える文例集!
メッセージの基本的な書き方やコツとマナー

結婚祝いを贈ってくれた方に感謝の気持ちを伝えたい場合は、新婚旅行のおみやげなどを差し上げるのもひとつ。その際に添えたいのが、結婚内祝いのメッセージ。新しい門出を祝ってくれた方々に感謝の気持ちを伝えましょう。より相手に喜ばれるための結婚内祝いメッセージの書き方・コツ・マナーをご紹介します。
結婚内祝いのメッセージを書くポイント

結婚内祝いは、挙式に欠席された方や招待できなかった方に報告を兼ねて贈るのが一般的になってきています。どんな式だったのか、親しい方は気になるでしょう。その場合は、結婚式の写真をメッセージに添えても良いでしょう。
また相手から品物をいただいた場合は、「その品物をとても気に入っている」、「喜んでいる」ことを書き添えると、より丁寧な印象に。感謝を伝えたあとは、近況報告やこれからの抱負を書きます。あまり長く書く必要はありませんが、幸せな家庭を作りたいという気持ちを伝えます。最後は相手が親しい関係でも、礼儀をわきまえた挨拶や、新居にお誘いするような言葉を添えてまとめます。
「かしこまった文章は苦手…」という方も多いと思いますが、大切なのは感謝の気持ちです。たとえ文章を書きなれていなくても、心を込めた文章であれば、相手もきっと喜んで受け取ってくれるでしょう。
結婚内祝いのメッセージを贈る際に気を付けておきたいこと
結婚内祝いのメッセージを贈る際には、あわせて贈るタイミングや避けるべき言葉・マナーも確認しておきましょう。
手紙で送る場合の便せん、封筒について
結婚内祝いに添えるお礼状は、感謝を伝える特別な手紙です。せっかくなら便せんや封筒も、こだわって選びたいですね。まず便せんは無地の白か罫線のみ入っているシンプルなものに。封筒は最も格式の高い白の二重封筒を選びましょう。横書きの手紙も増えていますが、目上の方に送るのであれば、縦書きが無難です。
時候の挨拶
時候の挨拶は、短くまとめられた「漢語調」と少しくだけた表現の「口語調」の2種類があります。目上の方には漢語調、親しい間柄には口語調を使います。
贈るタイミング
結婚祝いをいただいたら、まずは電話などで直接お礼を伝えます。結婚内祝いの品物とお礼状やメッセージを別に送る場合は、品物よりもお礼状が先に届くようにします。
結婚祝いをいただいてから挙式まで期間があく場合は、内祝いを送るのは挙式後でも問題ありませんが、お礼状は先に出しておき、感謝の気持ちをきちんと伝えるようにしましょう。入籍前に結婚祝いをいただいたら、入籍後にお礼状を出し、結婚の報告をします。
忌み言葉を避ける
忌み言葉とは、おめでたい場にふさわしくないと思われる縁起の悪い言葉や言い回しのこと。「別れる」「切れる」など、別れを連想させる言葉、「死ぬ」「病む」など不吉な言葉、再婚や不幸を連想させる言葉は避けましょう。「帰る」「戻る」は離婚や別居をイメージする方もいるので、例えば「帰宅」や「帰省」などと言い回しを変えましょう。「忙しい」の「忙」は「亡」が入っているので、忌み言葉にも該当します。「ご多用」や「いそがしい」など、ひらがなに変換すれば使えるものもあります。「流れる」「割れる」「四(死)」「九(苦)」なども忌み言葉になるので、使わないようにしましょう。
重ね言葉を避ける
重ね言葉とは、不幸が繰り返されることを連想させる言葉で、「再び」「しばしば」「いよいよ」「皆々様」なども避けるようにしましょう。「いろいろとありがとう」などは頻繁に使われがちですが、「たくさんの心づかいをありがとう」などの文章表現に変えた方が無難です。
自慢にならないように注意する
幸せな気持ちを伝えたいあまり、相手が不快に感じるようなのろけ話にならないように気を付けましょう。特に相手が未婚である場合は文面に配慮し、必ず読み直すようにします。感謝の気持ちをきちんと伝えられているか客観的に見直すことが大切です。
メッセージの構成パターン
(時候の挨拶が入る場合もあり)
- ① いただいた結婚祝いに対する感謝の気持ち
- ② これから始まる新生活への抱負
- ③ 品物をいただいた場合は実際に活用している旨を伝える
- ④ 今後もお付き合いをお願いする言葉や、相手を気遣う言葉
- ⑤ 新郎新婦の名前(旧姓)、新居の住所や連絡先
結婚内祝いのメッセージの文例を贈る相手別にご紹介

基本的な文例①
この度は、結婚祝いをいただきありがとうございました。
これから、二人で力を合わせ、温かな家庭を作っていきたいと思います。
ささやかではありますが、内祝いの品をお贈りします。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
基本的な文例②(①よりもかしこまった表現にしたい場合)
謹啓
○○の候 ○○様におかれましてはご清祥のこととお喜び申し上げます
この度は 私どもの結婚に際し過分なお祝いを賜り誠にありがとうございました
お礼のしるしに 心ばかりの品をお贈りします ご笑納いただければ幸いです
新居での生活にも慣れ始めたところです
今後は二人で力を合わせ 明るい家庭を築いていく所存です
今後も温かくご指導くださいますようお願い申し上げます
末筆ながら ○○様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます
敬白
令和○年○月○日
住所
氏名
○○○○様
目上の方へ
この度は私どもの結婚に際し、ご丁寧なお祝いをいただきありがとうございました。今後はいただいたご祝辞を大切に、温かな家庭を築きたいと思います。ささやかではございますが、心ばかりの品を送らせていただきます。
未熟な私どもですが、今度ともご指導ご鞭撻をいただけますようお願い申し上げます。
※「まだまだ未熟」と書かれがちですが、これは重ね言葉になるので避けましょう。
謹啓 ○○の候 ○○様におかれましてはご清祥のこととお喜び申し上げます
この度は 私どもの結婚に際し過分なお祝いを賜り 誠にありがとうございました
お礼のしるしに心ばかりの品をお贈りします ご笑納いただければ幸いです
新居に落ち着いて○週間たち ようやく慣れてきたところです
今後は二人で力を合わせ 明るく楽しい家庭を築いていく所存です
今後とも温かくご指導くださいますようお願い申し上げます
末筆ながら ○○様のご健康とご多幸を心より申し上げます 敬白
親戚へ
拝啓 さわやかな○○の日が続いておりますが 皆様いかがお過ごしでしょうか
この度は私どもの結婚に際し 心のこもったお祝いをいただきありがとうございました
ささやかですが心ばかりの品をお贈りします
ようやく新居も片付きました 近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください
二人で温かい家庭を築いていきたいと思っておりますのでこれからも変わらずご指導をよろしくお願い申し上げます 敬具
両親へ
(自分の両親の場合)
結婚のお祝いをありがとうございました。
これからは○○さんと2人でお父さんとお母さんのような楽しい家庭を作りたいと思っています。
これからもよろしくお願いします。
(義理の両親の場合)
こんにちは。
○○日が続いておりますが、お父様お母様におかれましてはお変わりなくお過ごしのことと思います。
このたびは○○さんとの結婚に際し過分なお心遣いをいただき、深く感謝を申し上げます。
ささやかながらこころばかりの品をお送りいたします。
今後ともご指導賜りますよう、よろしくお願いいたします。 敬具
先輩へ
(既婚者の場合)
私どもの結婚に際し、お心づかいをいただきありがとうございました。これからは○○さんのようなご家庭を目標に笑顔の絶えない家庭を作っていきたいと思います。ささやかですが、内祝いの品をお贈りします。
これからもご指導いただきますようよろしくお願いします。
※目上の方には「お言葉を胸に」「○○さんに習い」など、相手を立てると好印象です。
親しい友人へ
(未婚の場合)
○○ちゃん、心のこもったお祝いをありがとう! 本当に嬉しかったです。
いただいた素敵な△△、毎日気に入って使っています。
ささやかですが、お返しを贈ります。
これからも変わらず、どうぞよろしくお願いします。新居にも遊びに来てね!
結婚式に出席できなかった方へ
この度は、私どもの結婚に際し温かなお心遣いをいただきありがとうございます。
○月○日に無事挙式いたしました。今後は2人で明るい家庭を築いていきたいです。
ささやかですが、内祝いを贈らせていただきますので、ご笑納ください。
お近くにお越しの際は、ぜひ新居にお立ち寄りくださいね。
※遠方の方には、新居へ招く一文を加えると親しみが感じられます。
自分たちの幸せな気持ちを自分たちらしく報告すれば、相手も温かい気持ちに!

最近では、挨拶状はカードタイプが多くなり、「拝啓」「敬具」や時候の挨拶をつけない場合も。その場合でも、名前(旧姓)や住所、連絡先は必ず入れるようにしましょう。
結婚内祝いのメッセージは、夫婦となった二人から初めて贈るメッセージでもあります。自分たちの幸せな気持ちを報告し、今後の抱負だけではなく、祝ってくれた相手への感謝をきちんと伝えるようにしましょう。

-
笹西 真理
株式会社 トゥルース代表取締役
社団法人 日本マナーOJTインストラクター協会 創設者会長
マナースクール「Grace」主宰元国内系国際線CAとして5年半実績を積んだ後、大手コンサルティング関連会社において、飲食・小売関連の販促・広告戦略を主とするコンサルタントとして活躍。2005 年に株式会社 Truth を設立。飲食・物販・SC・各種団体・大学など、マナー・接遇・コミュニーションを中心とした社員教育、人材育成に携わる。また、2010 年一般社団法人日本マナー OJTインストラクター協会を立ち上げ、代表理事に就任。現在、約 400 名の講師と共に「サービス業の未来を輝かせる」をミッションに全国を飛び回る。
▼著書
『どこまでOK?がすぐわかる! 冠婚葬祭の新マナー大全』(成美堂出版・2019年2月出版)、『気くばりの教科書』(泰文堂)
『いつもうまくいく人の習慣』(リンダパブリッシャーズ)