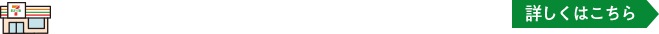快気祝いとは?
全快祝いとの違いや、定番のギフト、贈る際のマナーまで解説

快気祝いとは、病気見舞いをいただいたあと、お返しとして贈るものです。「病気が残らない」「洗い流して忘れる」という願いから、残らない品物を選びます。見舞いの品をくださった方は、「病状が悪くなっていないか」、「無事に退院されたか」など、随分と心配されているはずです。快気祝いを相手に贈り、心から安心していただくのが大人の振る舞いだと言えるでしょう。
快気祝いとは

もともと快気祝いとは、自分の病気やケガの回復を祝い、本人の名前をつけて贈るもの。例えば、本人からお世話になった方々へ全快の報告をする際やお見舞いのお礼をかねた祝宴を開いた際などに贈るのが通例でした。現在では、いただいた見舞いの品に対して、退院や回復の報告を兼ねたお礼として贈ります。ちなみに「快気祝い」と「全快祝い」は、ほとんど同じ意味で使われる場合が多いです。
快気祝いと全快祝いとの違い
快気祝いも全快祝いも、退院したときに贈るものですが、回復の度合いで使い分ける方もいます。例えば病気やケガが完治した状態で贈る場合は「全快祝い」。完治はしておらず、引き続き通院や自宅療養を行っている状態で贈る場合は「快気内祝い」となります。現在では全快がしばらく難しい場合は、「御礼」「お見舞い御礼」などでお返しするのが一般的です。
快気祝いでは何を贈るべき?

快気祝いには、残らずなくなるものを選びましょう。たとえばお菓子、お茶やコーヒーなどの飲み物、洗剤やせっけんなどは快気祝いにピッタリ。
果物類も食べたらなくなるものであり、なおかつ健康的なイメージもあるので近年人気です。
最近では、カタログギフトに人気が集まっています。また、商品券やギフトカードなどの金券類や現金を贈ろうと考える人もいるかもしれませんが、目上の方には避けた方が無難でしょう。
快気祝いに避けるべきもの
「寝付く」を連想させる寝具類や「根付く」と言われる鉢植えのお花などは、縁起が悪いとされています。候補として選ばない方がよいでしょう。
快気祝いを贈る際のマナーとは?

入院中に何かと気遣ってくださった方やお世話になった方には、きちんとした振る舞いで感謝を伝えたいですよね。ここで快気祝いの相場や贈る時期について、ご紹介します。
相場
金額の目安は、頂いたものの半額から3分の1程度が目安です。多額のお見舞い金をいただいた場合は、無理のない範囲の品物でよいでしょう。
万が一病気が回復せずに亡くなってしまった場合は、快気祝いを贈る必要はありません。もしお礼を贈る場合は、「御見舞御礼」という名目でよいでしょう。その場合は、お香典返しと御見舞御礼の品物を両方用意し、四十九日の忌明け後に、2品を同時に配送するのが一般的です。意味合いを分ける為に別の品物にし、それぞれの「のし紙」の弔事包装で用意しましょう。
一緒に送る場合には、御礼状として忌明け挨拶状とお見舞礼状の2種類を付けると丁寧です。
贈るタイミング
病状にもよりますが、ほぼ回復し社会復帰が早い場合は、目安として退院後10日~1か月以内に返礼をするとよいでしょう。
退院後も通院する場合や、自宅療養となる場合は、完治まで時間がかかることも想定されます。早くお返しをしたいなら一旦退院祝いとしてお返ししてもよいですが、受け取る側としては完治の報告の方がより安心できるでしょう。時間がかかってもあまり焦ることなく、回復してから贈るほうがベストです。
もちろん、入院中や退院直後ですでに完治した方は、すぐに報告やお礼をしても問題ありません。
のし
「病気は二度としたくない」「再び病気を繰り返さないように」といった意味で、ほどけやすく何度も結び直せるちょう結びではなく、結び切りの水引がついたものを使います。表書きは、上に「快気祝い」、下に本人の姓もしくは姓と名を入れましょう。全快していない場合は、「御見舞御礼」「退院内祝」とすることもあります。
挨拶文、メッセージ
快気祝いは、回復の報告や感謝の気持ちを伝える贈りもの。挨拶文やメッセージカードを添えましょう。
また、病気やケガは喜ばしいものではありませんね。「ますます」「重ね重ね」「くれぐれ」「次々」「いろいろ」「いよいよ」「再び」といった重ね言葉は使わないように注意しましょう。
改まって封書で書く場合は、下記の構成が一般的です。
【一般的な構成】
- ① いただいた結婚祝いに対する感謝の気持ち
- ② これから始まる新生活への抱負
- ③ 品物をいただいた場合は実際に活用している旨を伝える
- ④ 今後もお付き合いをお願いする言葉や、相手を気遣う言葉
- ⑤ 新郎新婦の名前(旧姓)、新居の住所や連絡先
メッセージカードであれば②~⑤をまとめて書きます。相手の心配を取り払うような内容を含めておくとよいでしょう。例えば「退院後しばらくは身体を気遣います」など、近況を詳しく書いておけば、相手も安心できます。
【お礼状】
・目上の方
お見舞いに来てくださった場合
拝啓 〇〇の候 〇〇様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。
入院の際にはわざわざお見舞いにお越しいただき、過分なお気遣いまで賜り厚くお礼申し上げます。
ご心配をおかけいたしましたが、おかげさまで快方に向かい〇月〇日に無事に退院いたしました。
しばらくは自宅療養し、体力の回復に努めます。本復の際は改めてご挨拶に伺いたいと思っております。内祝いとして心ばかりの品をお届けいたしますのでご笑納くださいませ。
皆様のご健康とご多幸を心からお祈りしております。
まずは略儀ながら書中をもって御礼かたがたご挨拶申し上げます。敬具令和〇年〇月〇日
お見舞いを届けてくださった場合
拝啓 〇〇の候 皆様にはお健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
この度は入院中に丁重なるお見舞いを賜り誠にありがとうございました。
おかげさまで順調に回復し、無事に退院いたしました。
これもひとえに皆様の温かい励ましのおかげと感謝申し上げます。
なお内祝いの印として心ばかりの品をお届けしますので、ご笑納くださいませ。
末筆ながら皆様のご健康とご多幸を心からお祈りしております。敬具令和〇年〇月〇日
拝啓 〇〇の候 〇〇様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。
私の入院中は、ご丁寧なお見舞いをいただき、誠にありがとうございました。
術後の経過もよく、〇日に退院の許可が出ました。現在は自宅で療養中です。
今後も定期的に通院はいたしますが、仕事は間もなく開始できそうです。
これからは健康管理に努め、皆様にご迷惑をおかけしないように過ごしていきます。
なお内祝いの印として心ばかりの品をお届けしますので、ご笑納くださいませ。
まずは書中にてお礼とご挨拶を申し上げます。敬具令和〇年〇月〇日
※仕事復帰に関しては、しばらく安静にする必要がある場合や、リハビリなど通院が必要なときは、「社会復帰まではもう少し時間がかかる状態で、現在はリハビリにつとめております」と書き換えるなど、現状況をできるだけ詳しく記します。
【メッセージ】
・職場の上司、同僚に贈る場合
先日はご多忙の中、心温まるお見舞いをいただき誠にありがとうございました。
ご心配をおかけしましたが、〇月〇日無事に退院いたしました。
これも皆様にお気遣いいただき、治療に専念させていただいたおかげと感謝しております。
しばらくは自宅にて療養し、〇〇より出社する予定です。
ささやかながら心ばかりの品をお届けしますので、ご笑納ください。
復帰後はより一層業務に精励いたしますので、何卒よろしくお願いいたします。
・心配をかけてしまったことに対するお詫びを伝えたい場合
この度は、皆様に大変なご迷惑をおかけし、心苦しく思っております。
幸い大事に至らず、〇週間の入院で済みました。復帰後はこのようなことがないよう、健康管理に十分留意いたします。変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます。
ささやかながら心ばかりの品をお届けしますので、ご笑納ください。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
・親しい友人に贈る場合
先日は忙しい中お見舞いに来てくれてありがとう。
おかげさまで、〇月〇日に無事退院することができました。
〇〇ちゃんの励ましのおかげで、予定よりも早く退院できました。
しばらくは家でゆっくりと療養しますが、来月には外出できそうです。
ささやかですが、心ばかりのお礼です。
また会えるのを楽しみにしています。
・本人に代わって、家族の立場で贈る場合
先日は父の入院中にお心のこもった励ましのお言葉とお見舞いを頂戴しまして、心より感謝申し上げます。おかげさまで〇月〇日に無事退院いたしました。
現在は自宅にて療養中ですが、順調に回復しております。
心ばかりの品ですが、お納め下さい。
お心遣いに心から感謝を申し上げますとともに、回復のご報告とさせて頂きます。
心身の回復を願ってくれた相手に、最大限の感謝を伝えましょう

病気やケガをすると、周囲の方のあたたかいメッセージやご支援が、よりありがたく感じられますよね。品物の選び方、メッセージの書き方に気をつけるのも大切ですが、何よりも心身を充分に回復させることが、相手にとって一番の喜びとなるはず。しっかりと静養をとったうえで、相手に喜んでもらえる品物とメッセージを準備しましょう。

-
笹西 真理
株式会社 トゥルース代表取締役
社団法人 日本マナーOJTインストラクター協会 創設者会長
マナースクール「Grace」主宰元国内系国際線CAとして5年半実績を積んだ後、大手コンサルティング関連会社において、飲食・小売関連の販促・広告戦略を主とするコンサルタントとして活躍。2005 年に株式会社 Truth を設立。飲食・物販・SC・各種団体・大学など、マナー・接遇・コミュニーションを中心とした社員教育、人材育成に携わる。また、2010 年一般社団法人日本マナー OJTインストラクター協会を立ち上げ、代表理事に就任。現在、約 400 名の講師と共に「サービス業の未来を輝かせる」をミッションに全国を飛び回る。
▼著書
『どこまでOK?がすぐわかる! 冠婚葬祭の新マナー大全』(成美堂出版・2019年2月出版)、『気くばりの教科書』(泰文堂)
『いつもうまくいく人の習慣』(リンダパブリッシャーズ)